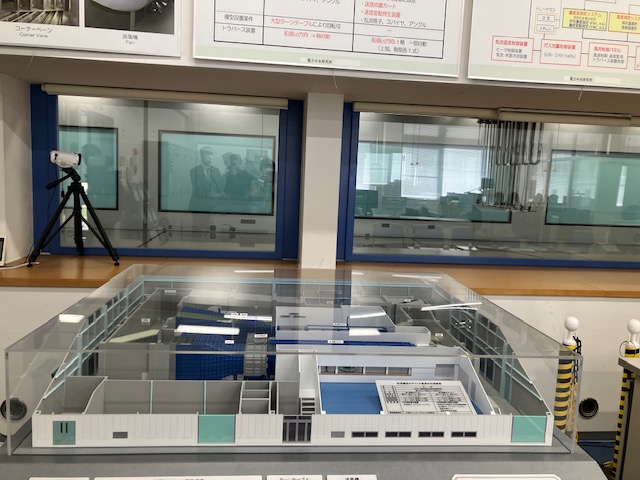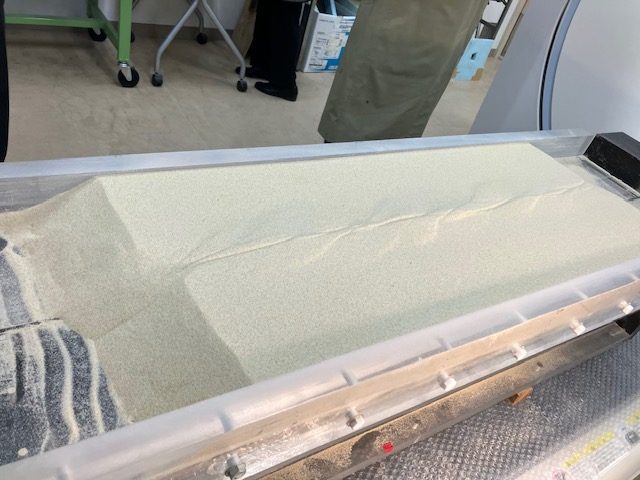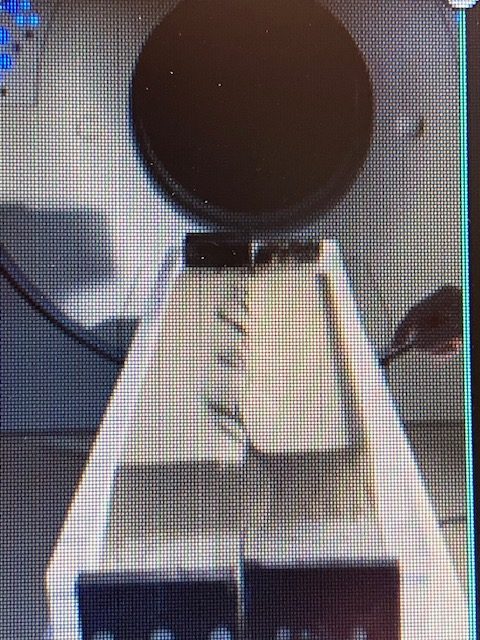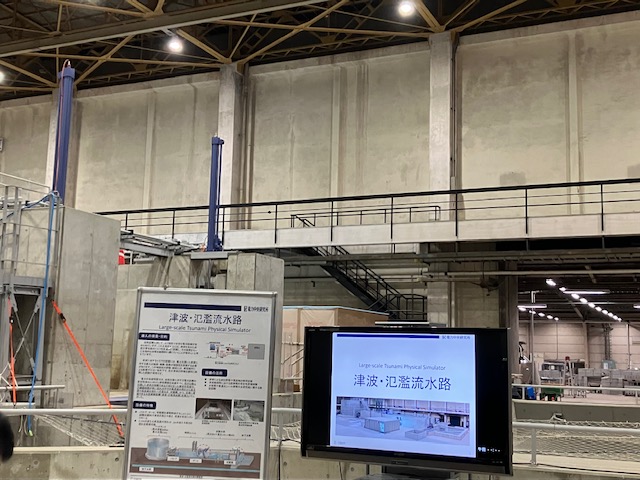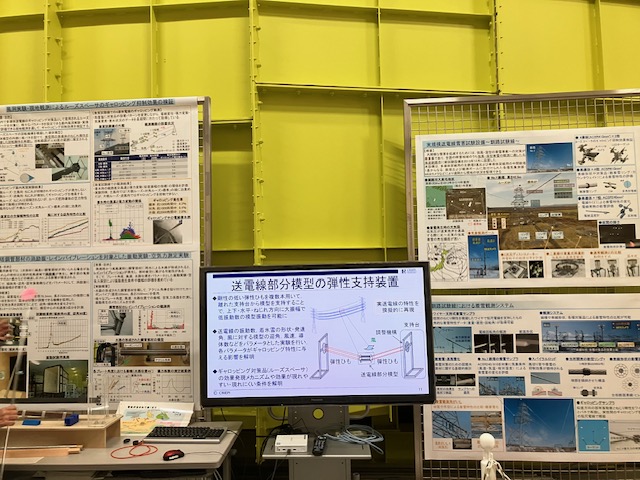北陸新幹線に乗車したとき、座席のポケットに入っている「トランヴェール」を読むことが楽しみだ。以前に沢木耕太郎氏が「旅のつばくろ」という題でエッセイが掲載されていて、その後「旅のつばくろ」「続・旅のつばくろ」が出版された。すぐに購入し、Kindleでいつも持ち歩いている。
最近、トランヴェールで「The History of JRE」のページが始まり、第1回が「黄色い線の呼びかけから黄色い点字ブロックに」という題名での取り組み紹介があった。
以前は「危ないですから黄色い線の内側に下がってお待ちください」というアナウンスが、最近「黄色い線」が「黄色い点字ブロック」に変更になっている。素晴らしいなあ~と思っていた。そのきっかけとなったこととその取り組みが、トランヴェール5月号の「The History of JRE」に掲載されていたのだ。
2022年11月に、高崎駅のある一人の駅員の強い訴えが、高崎駅社員の心に響き、呼びかけが「黄色い点字ブロック」に変わったそうだ。他の駅でも「黄色い点字ブロック」という呼びかけに変わっているところが多い。こうした呼びかけで、健常者に「点字ブロック」が改めて認識されるようになった。
上司に「黄色い点字ブロック」という呼びかけへの表現統一の徹底を提案したその駅員も視覚に障害のある人で、駅階段の点字ブロック上に人が集団でいたために迂回して転落した全盲者のことを聞いたのが、今回の訴えのきっかけとなったそうだ。
JRのこうした取り組みが、少しずつ健常者の意識も変わっていくだろう。
点字ブロックの正式名称は「視覚障害者誘導用ブロック」という。1965年に岡山県の男性が発明し、1967年に世界で初めて岡山県の交差点に敷設されたという。そして1970年代初めに高田馬場駅で大規模に敷設され、次第に全国に広まった。高田馬場駅は、近くにある日本点字図書館を利用する視覚障害者の乗降が多いからだろう。
一人の強い想いが全国に、世界に広がっていくのだ。この記事を読んでとても気持ちいが暖かくなった。